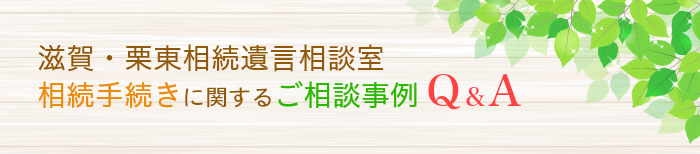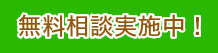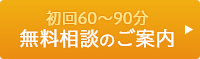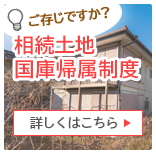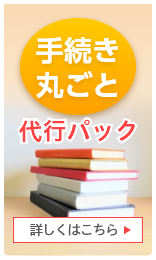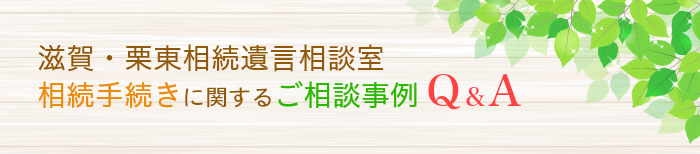
遺言書の作成
2022年12月02日
Q:行政書士の先生、父の相続について誰が相続人になりますか?(近江八幡)
先日、近江八幡で暮らしていた父が亡くなりました。遺品の中に遺言書が見つからなかったので、相続について親族と話し合っているのですが、誰がどのくらいの割合で相続するのかが分からず遺産分割を進められないでいます。相続人は、母と私と弟になると思いますが、弟は3年前に他界しておりその子どもが相続人になると聞きました。そうした場合、法定相続分はどのようになるのでしょうか。教えていただきたいです。(近江八幡)
A:法定相続分は相続順位により、確認できます。
民法では誰が遺産を相続するのか定めており、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。なお、配偶者は必ず相続人となり、各相続人の相続順位により法定相続分は変わってきます。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人にはなりません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様の場合、お父様の相続の法定相続分は、配偶者であるお母様が1/2、子供であるご相談者様が1/4、弟様のお子様が1/4となります。弟様のお子様が2人以上いる場合にはお子様の人数で1/4の財産を割ります。
ちなみに、基本的に遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を自由に決めることができますので、必ずしも法定相続分で相続をしなければならない訳ではありません。
今回のご相談者様の場合の法定相続分については上記になりますが、家族構成などによって相続人や法定相続分の割合などは変わってきます。法律の知識がないと、ご自身での判断が難しいケースもございますので、相続について疑問点がある場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、近江八幡の皆様の相続に関するお悩みをサポートしております。近江八幡にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なことがある方、または専門家に相談したい方は、お気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。
2022年09月02日
Q:父が遺言書を残していますが、母との連名の遺言書だとわかりました。連名の遺言書について効力はあるのでしょうか?行政書士の先生にお話しをお伺いしたいです。(野洲)
父が亡くなり、自宅の片付けをしていた際に父が書いた遺言書が見つかりました。母はこの遺言書を作成したことを知っており、内容についても把握しています。内容は、父所有の野洲の自宅と、先代より相続した野洲市外の土地、それと母名義の財産についても記載があり、署名も父と母の連名でしたとのことです。母親は、この連名の遺言書で問題ないだろうと言っているのですが、法的に有効な遺言書になりますか?(野洲)
A:ご夫婦(婚姻関係)であっても、二人以上の署名がされた遺言書は無効となります。
連名での遺言書についてですが、民法上2人以上の物が同一の遺言書を作成することはできない「共同遺言の禁止」に該当するため、今回のご相談者様のケースについては法的に無効な遺言書ということになります。
遺言書は、「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものとして作成されます。このことから、遺言者が複数であった場合に片方が主導的な立場で作成をしたという可能性が否定できないため、遺言者の自由な意思が反映されていないものとみなされます。
そして、遺言書の撤回という面でみても、連名の場合には遺言者の自由が奪われることになります。遺言書は作成した者が自由に撤回することが可能ですが、連名の場合ですと片方からの同意が得られなければ内容の撤回ができないという事になります。
法律で定められている形式で作成されていない遺言書は、原則無効となります。ご自身の最終意志である遺言書ですから、第三者が介入しその意思が自由にならないようではその遺言書は意味を持ちません。遺言書の作成をご検討される場合、確実にご自身の意思を大事な家族へ残すのであれば、遺言書や相続手続きに特化した専門家へと相談のうえ作成されることをおすすめいたします。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、野洲のみなさまの遺言書や相続手続きの専門家として多くのご相談をいただいております。野洲にお住いの皆様の相続に関するお困りごとに幅広く対応が可能でございます。遺言や相続手続きに詳しい専門家が初回の無料相談より親身に対応をさせていただきます。
まずはお気軽に当相談室へとお問い合わせください。所員一同、野洲の皆さまのご来所を心よりお待ちしております。
2022年07月01日
Q:行政書士の先生、遺言書にない財産はどのように扱えば良いのでしょうか。(栗東)
行政書士の先生、はじめまして。遺言書のことで相談させてください。
私の両親は栗東に住んでいるのですが、先月頭に父が亡くなってしまいました。葬式は栗東の実家で行われ、遠方に住んでいる私も何とか休みをもぎ取って参列しました。
その後、再び家族全員で栗東の実家に集まり、たんすの中から見つかった遺言書の内容に沿って遺品整理を進めていたところ、祖父から受け継いだ栗東の土地が遺言書にないことに母が気づきました。
栗東の土地は特殊な形状をしていて活用のしようがないそうで、父も遺言書に記載するのを忘れてしまったのだと思われます。遺言書にない栗東の土地はどのように扱えば良いのか、教えていただけると助かります。(栗東)
A:遺言書にない財産は「遺産分割協議」にて分割方法を決定します。
遺言書にない財産は遺言書のない相続が発生した時と同様に、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、どのように分割するかを決定する必要があります。分割方法に相続人全員が納得した場合はその内容をとりまとめて「遺産分割協議書」を作成し、最後に相続人全員で署名・押印をして完成させましょう。
今回遺言書になかった財産は栗東の土地(不動産)ですので、お父様から相続した方に名義を変更する手続きの際にこの遺産分割協議書の提出が求められます。財産ひとつでわざわざ書類を作成するのは億劫に感じるかもしれませんが、必ず作成しておきましょう。
なお、遺産分割協議書の作成には決まった書式・用紙等はなく、手書きはもちろんのこと、パソコンを使用しても構いません。
遺言書にない財産が見つかった場合はこのような工程が必要になりますが、「記載のない財産の扱いについて」というような文言が遺言書にあった場合にはその内容に沿って相続するだけで済みます。
こうした文言は遺言書への財産の記載漏れを防ぐためのものであり、多数の財産を所有している場合等に活用されています。相続人全員で遺産分割協議を行う前に、まずはお父様の遺言書に上記のような文言があるかどうかを確認してみてください。
滋賀・栗東相続遺言相談室では豊富な知識と経験を備えた行政書士による初回無料相談を設け、栗東や栗東周辺の皆様が抱えていらっしゃる相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらずに、私どもにお話しください。
栗東の皆様、栗東で相続・遺言書作成について相談や依頼のできる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、滋賀・栗東相続遺言相談室の行政書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。
まずはお気軽にお電話ください
0120-172-690
営業時間 9:00~19:00(平日・土曜) ※事前予約により日曜・祝日も相談対応