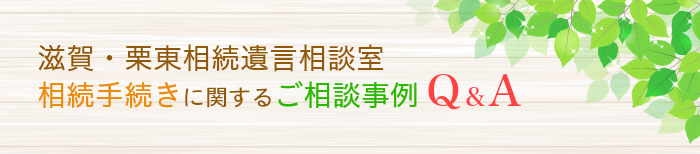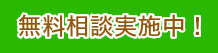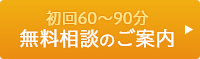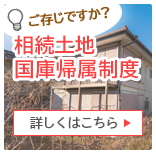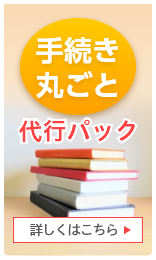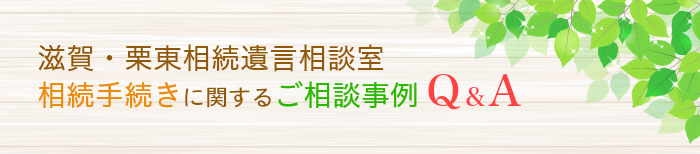
地域
2024年10月03日
Q:代襲相続になる場合の法定相続分の割合について行政書士の先生教えてください。(栗東)
先日、栗東に住む父が亡くなりました。葬儀を執り行い、母と遺品整理をしましたが、遺言書はなかったため法定相続分で相続手続きを進めようと思っています。しかし、法定相続分の割合が分からずに困っています。相続人は母、私(長男)、弟なのですが、弟は5年前に他界しています。弟には子供がいるのでその子供が相続人になるそうなのですが、この場合の法定相続分の割合が分かりません。法定相続分のそれぞれの割合を教えていただきたいです。(栗東)
A:法定相続分の割合は、まずは法定相続人の相続順位をご確認しましょう。
相続では、遺産を相続する人である「法定相続人」が民法で定められています。法定相続人は配偶者がいる場合、必ず相続人になります。配偶者以外の各相続人は相続順位が定められています。下記より各相続人の相続順位をご確認ください。
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※順位が上位の人がいる場合には下位の人は法定相続人ではありません。上位の人がいない場合もしくは亡くなっている場合に、次の順位の人に相続権が移ります。
上記より、法定相続人の確認ができたら下記の割合をご確認ください。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
今回の相続での各相続人の割合は、下記になります。
- お母様(配偶者)が1/2
- ご相談者様(子)1/4
- 弟様のお子様(孫)1/4 ※お子様が複数名いる場合、1/4をさらに子の人数で割る。
なお、上記の法定相続分の割合で遺産を分割しなければなならないわけではありません。遺言書がない場合の相続では、相続人全員での話し合いによって財産の分割内容を決めることもできます。これを遺産分割協議といいます。遺産分割協議の内容に相続人全員が合意したら、その内容を書面に書き出し、相続人全員が署名・押印をして遺産分割協議書を作成します。
ご相談者様の場合の法定相続分は上記になりますが、相続によって法定相続分の割合は変わるため、まずは相続人調査から着手するようにしましょう。相続手続きは複雑なものもあり、法律の知識がないと判断が難しい問題に直面することもあります。相続でお困りの方は、お気軽に相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、相続手続き専門の行政書士が栗東の皆様の相続手続きをサポートいたします。栗東で相続手続きの専門家をお探しの方は滋賀・栗東相続遺言相談室にお気軽にお問い合わせください。初回は完全に無料でご相談いただけます。栗東の皆様、お気軽に当相談室へお越しください。
2024年09月03日
Q:遺産相続の手続きを進めるためには遺産分割協議書が必須なのか否か、行政書士の先生にお尋ねします。(野洲)
野洲に暮らしていた父が亡くなりましたので、これから遺産相続の手続きを開始しようと思うのですが、遺産分割協議書についてわからないことがあります。
父が遺した遺産としては、野洲の実家、土地、預貯金と手元の現金を合わせて1,000万円ほどあります。家族同士で話し合い、これらをどのように分け合うかある程度目途は立っています。
遺産相続を経験したことのある友人からは、手続きには遺産分割協議書が必要なので必ず作成するようにと言われたのですが、相続人である母は、祖父の相続の際にはそんなもの作らなかったので不要だと言って聞きません。行政書士の先生、遺産相続の手続きには遺産分割協議書が必須なのでしょうか?(野洲)
A:遺産分割協議書は必須ではないですが、遺産相続の手続きで活用するほか、相続トラブルの回避にも役立ちます。
遺産分割協議書とは、遺産の分割方法について相続人全員で話し合い、決定した事項を書面にまとめたものです。この遺産分割協議書は遺産相続の手続きの際に使用するものですが、もし被相続人(故人)が遺言書を遺していた場合には、原則として遺言内容に沿って遺産相続手続きを進めることになりますので、相続人同士で遺産について話し合う必要もなく、遺産分割協議書の作成も不要となります。
今回の遺産相続において、亡くなったお父様が遺言書を遺していないのであれば、遺産分割協議書は作成しておくことをおすすめいたします。なぜなら、遺産相続では多額の現金が手に入る機会です。相続人同士の思わぬトラブルが生じる可能性もゼロではありません。実際に、遺産相続をきっかけに親族間に亀裂が生じるケースも少なくありませんので、話し合いで決定したことを遺産分割協議書に記し、相続人全員で署名捺印しておくと、後々の助けとなるでしょう。
■遺産分割協議書の活用シーン(遺言書がない場合)
- 不動産の相続登記(名義変更)の申請時
- 相続税申告時
- 金融機関での手続き時(遺産分割協議書を提示すると、金融機関の所定用紙にその都度相続人全員が署名捺印する必要がない)
- 遺産相続トラブルの回避
野洲の皆様、遺産相続の手続きは非常に煩雑で、手間も時間もかかります。遺産相続に不慣れな方にとっては疑問が生じる場面もあるでしょうし、負担も大きいため、遺産相続の専門家に手続きを依頼することもご検討ください。
滋賀・栗東相続遺言相談室では、野洲の皆様に向けて初回無料相談を実施しております。遺産相続に関する疑問やお悩みに丁寧におこたえしますので、野洲の皆様はどうぞお気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室までお問い合わせください。
2024年08月05日
Q:兄の相続手続きについて行政書士の先生にお伺いします。必要な戸籍を教えてください。(守山)
守山在住の50代の会社員です。先日、同じく守山に住む兄が亡くなりました。兄は一度結婚しましたが、離婚しており子供はいません。私たちの両親は他界していますので、相続人は弟の私のみになると思います。兄の身内は私のみになりますので、私が自分で調べながら相続手続きを進めていますが、兄弟間の相続の場合の戸籍請求はどのように進めればよいのでしょうか?兄弟の戸籍請求は大変だという話も聞きました。相続手続きに必要な戸籍について教えてください。(守山)
A:兄弟の相続手続きで必要な戸籍は下記になります。
相続手続きでは基本的には下記の戸籍を取り寄せます。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
兄弟相続では上記の戸籍に加えてさらに下記の戸籍が必要となります。
- 被相続人の両親それぞれの出生から死亡までのすべての戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍からは被相続人に配偶者や子供はいないかを確認することができます。この戸籍により、被相続人に認知している隠し子や養子がいたことが分かった場合、相続人はその子になりご相談者様は相続人ではありません。
そして、兄弟の相続では両親の出生から死亡までのすべての戸籍により、両親が亡くなっていること、被相続人に他に兄弟姉妹がいないかを確認することができます。
上記でご説明させていただいた戸籍はいずれも第三者に法定相続人は誰かを証明するために必要になります。
戸籍は複数回転籍している方が多く、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を請求するには被相続人の最後の戸籍から出生時の戸籍までさかのぼって読み取っていきます。(兄弟相続の場合、まずはご自身のご両親の戸籍から順に追っていく流れになります。)これらの戸籍の請求は過去に戸籍が置かれていたすべての市区町村に請求する必要がります。非常に手間と時間がかかる作業となりますので、戸籍収集が必要な場合には早めに着手することを推奨いたします。
このように、兄弟相続の際に必要な戸籍の収集は多くの書類を集めなければなりません。戸籍の請求だけなく、相続手続きはさまざまな手続きがあります。ご相談者様は日中お仕事もされているかと存じますので、相続手続きの専門家に依頼することも一つの方法です。守山や守山周辺にお住まいの方でお時間がなく、ご自身での相続手続きが難しいという場合は、お気軽に滋賀・栗東相続遺言相談室にお問い合わせください。守山で戸籍収集や相続手続き全般についてお困りの方は、滋賀・栗東相続遺言相談室にお任せください。初回は完全無料でご相談いただけますのでお気軽にご利用ください。
まずはお気軽にお電話ください
0120-172-690
営業時間 9:00~19:00(平日・土曜) ※事前予約により日曜・祝日も相談対応